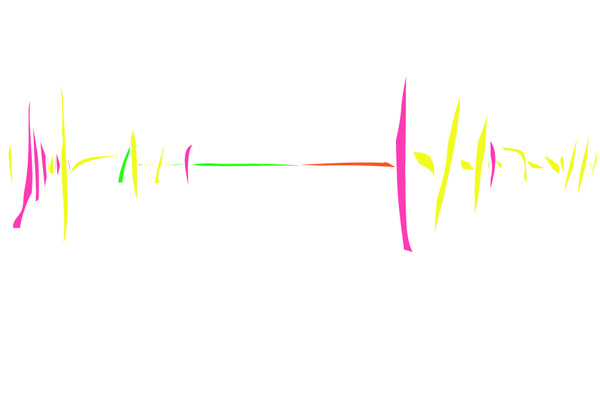モーリス・ルイスのオペレート・モデル
先に触れたモーリス・ルイスの「アンビII」は、〈ヴェール〉で薄く重ね合わされていた色彩の層が、はっきりと分離された作品だ。この「分離」に必要だったのが「奥行き」で、層が圧着され混ざり合って混濁した〈ヴェール〉の各レイヤーを、おのおの手前-奥に順次解体し、色彩の混ざり合いを回避しようとした。この引き離しは、後の〈アンファールド〉においては、「奥行き」ではなく、平面上の「並列」にとって変わる。モーリス・ルイスは、自作〈ヴェール〉のシリーズを形式的に分析し、その論理を自立的に展開していったことを簡単なモデルで図示してみよう。使用したのはMac(MacOS10.4)+Illustrator(10.03)。
〈ヴェール〉のシリーズは、いくつかの色彩の層が薄く=半透明に重なり合っている。その結果、重なり合った大部分の面積は、彩度が落ち、周囲のぶれた部分に彩度の高い絵の具の断片が見えているという構造をなす。これを図1に示す(クリックで拡大)。
この構造は、単純に色彩層に分割される(図2)。このモデルでは、「ダレット・サフ」のフレーム比率(画面中央の四角)に対して、5つの色彩層をマウスのフリーハンドで作成した。各色彩を重ね合わせる段階で60%の透明効果を指示している(ルイスがこだわったアクリル絵の具の粘度の調整を透明効果で代替したことになる)。
〈ヴェール〉のモデル図1の重ね合わされた部分、画面中央の大きなグレーを取り外し、周辺の彩度の高い部分だけを抽出したのが図3になる。Illustrator上では図1の重ね合わされた図形をパスファインダで分割指示し、中央混色部分を削除した。
ここで理解されるのは、この色面の形態が、ある種の「ゆらぎ」、手書きや染み込みによって形成される輪郭のぶれが必須だ、という事実だ。この揺らぎがなければ、周辺の彩度の高い取り残された部分が発生しない。ステラのストライプのような幾何形態、あるいはロスコのような完全なオールオーバーでは〈ヴェール〉の構造が成り立たない。ということは、〈ヴェール〉の特徴的な色面の形態は意識的な有機性を保持していることになる。
こうしてみると、後の〈アンファールド〉シリーズの構造が既に予感されることに気づく。残された色彩をIllustratorの整列コマンドで整列させてみたのが図4になる。
この整列=並列させられた色彩を、回転コマンドで向かって左は30度、右は-30度回転させてみる。結果図5が得られる。
この要素を適宜選択し、画面左右下辺に配置してみる(図6)と、〈アンファールド〉とほぼ同様の構造が得られる。
言うまでもなく、このモデルは作品から遡行的に構成したもので、モーリス・ルイスの思考の軌跡を再現したものではない。ただ、モーリス・ルイスの作品が、コンピュータのコマンドでオペレートしていくように形式的な見え方をしていることが分かり易く理解できるのではないだろうか。前のエントリでも書いたことだが、モーリス・ルイスは「良い感じの絵」を描こうとしていた画家ではない。構造的な分析を黙々と行いプログラムを走らせていた。あくまでその出力が「作品」なのだ。いわば彼が書いていたのは絵画そのものというより絵画のコードである。
しかし、その展開は論理的だが上記のように単線的ではない。〈ヴェール〉を解析して行く中で行われたオペレートが混ざり合ってしまっていた色の分離だとして、この分離は私のモデルのような流れ(色彩の並列化)になる前に、奥行きのイリュージョンを必要とした。これが「アンビII」の成立要因だろう。「アンビII」は、図7のような5階層に分割されているように見える。
中央の四角形の地、左に配置された大きく上下に貫通し色相が近く濃度の薄いストローク層、上のやや湾曲し濃度が上がり色相のバリエも増やされたストローク層、右の更に濃度があがり、短く曲がったストローク層、下の黒の層となる。これを奥から手前に、順次重ね合わせたのが図8になる。
これが〈ヴェール〉と異なるのは透明効果を使用していないことだ。これまた単純化されたモデルで、実際の「アンビII」にはステインによる混ざり合いetc.,〈ヴェール〉と共通する要素もあるが、しかしそれも十全に意識され理解されたうえでのオペレートであることは間違いない。このように「奥行き」によって分割され析出された色彩を、再度平面上に並列してみせたのが〈アンファールド〉であり、〈ストライプ〉もそこから発生していったと見ていいのではないだろうか。